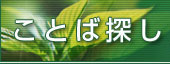■「今日のことば」カレンダー 2013年2月■
2024年 : 1 2 3 42023年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001年 : 11 12
| 2013-02-28 |
「どうせムリ」というメッセージをまわりから受け取ってきて 条件付けられてしまったとか、これまで成功体験がなくて、 自分を信じられないとは、いろいろでしょう。 あと 「信じてがんばって、でも期待とちがっていたらイヤだから、 はじめからムリと思っておけば、これくらいの不幸で済む」 みたいな意識の人もいます。 「あの人が好きなんだったら、自分から食事にさそってみれば?」 と言っても、「いい、自分なんてムリですよ」。 もし食事に誘ってふられるくらいなら「ムリ」と言って あきらめたほうがダメージは少ない、みたいな。 これはある意味、まじめな人でもあります。 「うまくいかない」の裏に、「うまくいかせなければならない」 という強迫観念があるのです。 「うまくいかなくてもしかたがない」と思えば、 「そうですね、やってみます」というふうになるはずです。 思い当たる人は、まず自分にそういうクセがあることを しっかり受け止めることから始めてください。 そこから必ず、変化が生まれると思います。 |
| 2013-02-27 |
↓ 《ポジ》1.成長材料…その悔しさをバネにまた一回り成長できる 2.勝負に張り合いがでてくる…敗北があるからこそ 勝負に熱くなれる 3.結果オーライ…あとから振り返ってみると、負けて よかったなと思えることもある 《ネガ》計画性がない ↓ 《ポジ》1.行動力がある…考える前にとりあえず動いてみる 2.土壇場に強い…いつでも予定を変更できるので、 怒とうの追い上げができる 3.常に排水の陣…自分を追いつめることで、 実力を発揮しようとしている |
| 2013-02-26 |
まずウサギが負けた本当の理由というのは…」(略) 「……実は、ウサギはカメを見たからです」 「……」 「なぜカメが勝ったか? それは、ウサギを見ずに、 自分のゴールだけを見続けたからです」 「……!」 「私がなぜ、このたとえ話をみなさんにしているか わかりますか?」 人生というのはとかく自分以上の能力の人を見て 劣等感を持ったり、不快な感情を持ったり、 やるべきことをやらず、結果的にその気持ちが 「負け」の現象を作ったりすることがあります。 また、ある人は、自分の能力以下の人に目を向けて、 仕事をサボったりすることもでてくるでしょう。 ですが、本当の勝利者となる人というのは、 常に自分のペースを見失わず、 ゴールに向かって歩み続けている人です。 人生の成功は、決して早い人が勝つとは限らない。 強い人勝つとは限らない。 本当に勝つ人というのは…そうです! あきらめずに、自分の目標を見失わずに歩み続ける人です。 その人が、最後に勝つんです」 |
| 2013-02-25 |
考えはすぐに思い込みとなって固まる。 この思い込みはあまりに習慣的になっていて、 自分では気づかないことも多い。 思い込みは結果を生む。 どのような思い込みをするかで、落胆してあきらめるか、 または満足して建設的な行動が獲れるかどうかが決まる。(略) いちばん大事なのは、自分の信念は思い込みであって、 事実ではないかもしれないと気づくことだ。(略) 誰も自分を雇ってくれない、愛してくれない、 自分には能力がない、と思い込んでいるからといって、 それが事実だということにはならない。 一歩後ろに下がってこの思い込みを一時保留し、 自分の考えが正しいかどうか確かめる間だけでも、 悲観的な説明から少し距離をおいてみることが必要だ。 |
| 2013-02-22 |
どうやって生計をたてるかというような、私たちがある程度 選択の余地を持っているすべて領域に関して、 どのような考え方を持っているかによって、実際にその領域を コントールする能力が減りもすれば、増しもする。 私たちは種々の事柄に反応してものを考えるだけでなく、 考え方によってその結果として起こる事柄を変えることもありうる。 たとえば、もし、私たちが子どもの将来になんの影響も 持てないだろうと考えていると、何かをしなければならない時に、 やる気が起きない。 「どうせ自分が何をしても状況は変わらない」という考えが 行動を起こすのをはばむのだ。 そして、自分が子どもに対して持っているはずの影響力を、 子どもの仲間や先生やその時々の状況にうゆだねてしまう。 |
| 2013-02-21 |
言葉を多く使っています。 いまでは「一所懸命」と書く人が少なくなりましたが、 私は両者を使い分けたいと思っています。 もちろん、「一生懸命」という言葉も辞書に載っていますから、 間違いではありません。 ただし、「一生」というのはとても長い時間ですから、 多くの状況は「一所懸命」のほうがふさわしいでしょう。 そして「一所懸命」を続けることが、 「一生懸命」につながるわけです。 まずひとつのところに集中し、それをやり続けることで、 「一所懸命」の連続が「一生懸命」になります。 |
| 2013-02-20 |
はじめてエネルギーがでてきます。 いまの時代は、あらゆることについて、結果が約束されたことや、 未来が保証されていることを求める人が多くなりました。 そのために、 「あなたがこうしたら、私たちの会社はこうしますよ」 という約束が、細かくなされています。 人々はそういうことにすっかり慣らされてしまい、 冒険をしようとする人が少なくなりました。 その結果として、 エネルギーがでない人間になってしまったわけです。(略) しかし、約束も保証もないからこそ、 みんな一所懸命に取り組みます。 仮に、 「あなたがこのようにしたら、一反あたりお米が十俵獲れます」 と決められていたら、十俵の努力しかしなくなるでしょう。 一所懸命にがんばっても、六俵しか獲れないかもしれないし、 もしかしたら十二俵獲れるかもしれない。 だからこそ、なんとか努力しようという気持ちが 生まれてくるのです。 |
| 2013-02-19 |
足踏みしたって 靴底が 減るだけやで ◎明日への扉は 自動ドアとちゃうで。 自分の手で 開けるんや |
| 2013-02-18 |
結構勇気がいることです。 それに「教える」という言葉を聞いて、 構えてしまう相手もいるでしょう。 そんなときに役立つ、相手が自然にいいことを 教えてくれるようになる3つの魔法の言葉があります。 1つめは、「すごいですね~」 次に、「なるほど~」 最後は、「おもしろいですね~」です。 この3つの言葉を口癖にしてください。 頭文字をとると「す・な・お」となります。 会話をしていて、相手からこのような言葉が返ってくると、 人はうれしいものです。 そして、もっと話してあげたい、 もっと教えてあげたいと思ってしまうのです。 「す・な・お」な心でまわりを見渡せば、あなたの人生を 豊かにしてくれる「師」は無数に存在しているはずです。 |
| 2013-02-15 |
本当はそんなことを望んでいないのに、周りから言われたとか、 誰かに期待されたとかで目標を立ててはならない。 繰り返すが、生物は「したいことしかできない」のだ。 結局のところ、本心が望んでないウソの願望は、 他の小さな願望とぶつかりあって負けてしまうことになる。(略) 願望を大きく育てることができれば、今まで面倒くさかったり、 嫌だと思っていたことも、その願望をかなえるために 「やりたい」ことに変わる。 単に「痩せたい」と思っているだけでは「甘い物を食べたい」 という願望に負けてしまうが、 「痩せることで美しくなれば自分に自信がもてるし、人と会うのが 楽しくなる、そうなれば、好きになった異性に振り向いて もらえたり、仕事も今まで以上にうまくいくかもしれない」 このように、『願望』に『想像』という栄養を与え続ければ、 甘い物はいつしか『食べたい』ではなく、 『食べたくない』ものに変わっているはずだ。(略) つまり、頑張るための方法は、 ↓ 『頑張らなければならない』 ↓ 『頑張りたい』 この状態を自然に導くことなのだ。 |
| 2013-02-14 |
「光らせている人が、光っている人」 これは、財団法人修養団の元伊勢道場長、 中山靖雄先生の言葉です。(略) 「光らせている人が、光っている人」とは、奥が深い言葉です。 おのれの人間力を磨くには、 自分ばかり磨いても仕方ないとも解釈できます。 自分を際立たせないと懸命になるより、まず、 人をひからせるようにする…そうしてこそ自分が光り、 結果として人間力も増すのではないでしょうか。 人を光らせるといっても、 難しいことをするわけではありません。 聞き上手になるのもよし、食事に行ったお店のスタッフを 光らせる、そんなことでもいいと思います。 人を光らせ、自分を光らせるための修養の場は、 いたるところにあると思います。 |
| 2013-02-13 |
どれだけ自分のみっともなさを見せられるか、 そこで人間力もはかられるのです。 東野君は、笑いを取りたい自己紹介だと、 「あごがしゃくれている」という自分の顔立ちを切り口にしています。 「僕のあだ名、子どものときについたのが、まが玉ですねん。 そりゃ、あんまりだろうというんで、 次のあだ名がカシューナッツ。 もっとお洒落に言おうといってくれるやさしいやつがいて、 ペイズリー柄。みんな名字のもじりや動物系のあだ名なのに、 僕だけ模様でっせ。ひどすぎますやん。 で、中学で英語の授業が始まったとき、ほっとしましたがな。 新しくつけられたあだ名は、「ロングロングアゴー」ですねん」 こうした「かっこ悪い自己紹介」を100回も200回も、 繰り返すうちに、「絶対に笑ってもらえる自己紹介」が できあがっていくのです。 |
| 2013-02-12 |
「いま何がいちばん何がつらいですか?」 という言葉がいちばんしっくりくるのではないかと思う。 私がもし患者の立場であったら、 まずそう尋ねてほしいと思う言葉だからである。 私の、この「いま何がいちばんつらいですか?」 という問いかけによって、二つのとても大事なことを 患者さんに同時に伝えられるのではないかと思っている。 一つは、 「この医師は自分の肉体的、精神的なさまざまなつらさを 知ろうとしてくれていること」 もう一つには、 「そのつらいことに対して、何らかの手だてで対処し、 支えようとしてくれていること」 この二つが患者さんの心に 同時に伝わるのではないかと思うのである。 |