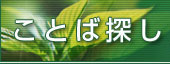■「今日のことば」カレンダー 2025年11月■
2025年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112024年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001年 : 11 12
| 2025-11-11 |
■仕事の関係で不定期UPになっております。 バタバタとしておりで…すいません。 今しばらくよろしくお願いいたします。 ■自分のビジョン、目標を書き込む、お礼カード、 アファメーションカードとして幅広く使える、 便利で美しいカードです。 「無地のカード」好評発売中! ★「詳細、使い方など」 ★購入はこちらから 結局、発する言葉は 持っている言葉の総量で決まります。 言い換えれば、持っている言葉の数が少ない人は、 表現も浅くなります。 当然ですね。 組み合わせの数が制限されるわけですから。 私が尊敬してやまない作詞家の 故、阿久悠先生の言葉がこれです。 「たくさんの言葉を持っていると、 自分の思うことを充分に伝えられます。 たくさんの言葉を持っていると、 相手の考えることを正確に理解できます」 (生きっぱなしの記)阿久悠著より まさにこれです。 何かを伝えようとしたとき、 あなたが言いたいことは すべて言葉の組み合わせです。 あるいは言葉から派生するイメージです。(略) 「こういう意味の言葉を紡ごう!」 と思わない限り、絶対に浮かばない言葉。 だからこそ、言葉の仕入れが必要で、 組み合わせる材料が不可欠なのです。 |
| 2025-11-09 |
その人がいくら優秀であったとしても、 それが「話す」とか「書く」とか、 いわゆるアウトプットをしなければ 「いなかったこと」も同じなわけです。 「アウトプット=発信」をしない限り、 それは「存在しない」のです。 どんなに「自分は優れた哲学者なんだ!」と 力んでみても、具体的に表現しない限り、 「いないもの」なのです。 つまり「つもり」ではダメです。 「届いたはず」でもダメ。 伝えたい人に、伝えたいことがキチンと過不足なく 届いて初めて「言ったこと」になるわけです。 そう、はじめに言葉ありきなのです。 伝えようと思うなら、 伝わって欲しいと願うなら、 まず言葉にすることです。 それしかありません。 私たち、ビジネスに携わる人間に、 アイコンタクトなんてないのです。 |
| 2025-11-04 |
重要なパフォーマンスを実行する場面では、 「絶対に失敗したくない」 「より良いパフォーマンスを発揮したい」 という思いから、できるだけ慎重に動作を遂行しようと、 余計なことを考えてしまいます。 練習と同じ平常心を保つことができない状態で、 パフォーマンスを遂行してしまうと、 きっと失敗してしまうでしょう。 そこで有効なのが、ルーティンです。 ルーティンとは、いわば、 いつも同じ平常心に戻るための動作、とも言えます。 いつもの練習と同じルーティンを行うことで平常心を取り戻し、 目の前のパフォーマンスに集中することができます。 同じ動作を繰り返すことで自然とリラックスして集中でき、 その一連の動作の中で自動化されたパフォーマンスを 意識せずに(無意識に)実行することができるのです。 そこで、練習時に必要となってくることは、 本番を想定して(イメージが大事になってきます) 重要なパフォーマンスを含めて一連の動作を繰り返し、 繰り返し行うことによって「ルーティン」と呼ばれる 「決まりきった動き」に定着させていくことです。 本番では、いつもと同じ状況に戻るための動作 (ルーティン)を行うことで、重要なパフォーマンスを 意識することなく(無意識に)実行することができるのです。 |
| 2025-11-01 |
サトルさんは、コツコツ勉強するのは好きで得意でしたが、 教室に入って友だちや先生と接するのは 恐ろしくてたまりませんでした。 就職してからもそうです。 サトルさんは、教室や職場の人間関係、 つまりずっと社会を恐れてきました。 もっというと、人間関係が円滑に保てない自分の 社会性の低さから目を逸らしたくて、 みじめで愛されない自分を認めたくなくて、 「うまくいかせないのは、すべて中学の担任のせいだ」 と担任を責めることで問題を外在化して 否認してきたのです。(略) つまり、現実でうまくいかない理由を考える代わりに、 すべてを担任への恨みに変換してきたというわけです。 その結果、本人でも驚くほどに恨みが巨大化し、 コントロールを失い、たびたびサトルさんの 日常を阻害していたのです。 さて、サトルさんはどうすればいいでしょう? |