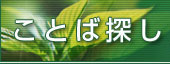■「今日のことば」カレンダー 2018年10月■
2025年 : 1 2 3 4 5 6 72024年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001年 : 11 12
| 2018-10-31 |
個人を競わせるからには、 その土台となる条件が同じでなければなりません。 しかし、実際には、まったく同じ条件で競わせることは ほとんど不可能です。 ある企業では、社長が成果主義を導入し、 若い社員を競わせ、成績に応じた給与を支払うようにしました。 すると、業績が悪くて給与を減らされた社員が どんどん辞めていきました。 社長は 「仕事ができない人間が辞めたのだから望むところだ」 と思ったようですが、実はとんでもない勘違いでした。 その会社では、社員一人ひとりに 担当地区を割り当てて営業させていました。 しかし、地域によってお客様のニーズに相当な違いがあり、 契約が取りやすい地域と非常に取りにくい地域が 存在していたのです。 残った社員は、特別に優秀だったわけではなく 担当地域に恵まれていただけ。 だから、辞めた人間が担当していた地域に回ると、 前任者よりも少ない契約しか取れないという結果になりました。 個人を競わせると、チームの雰囲気が悪くなるだけでなく、 チームとしての成長戦略そのものがダメになっていく 可能性があるのです。 |
| 2018-10-29 |
長い不安の波に沈んでしまった日本では、 誰でも、いつかはコミュ障になる可能性を秘めています。 あなたも、病むことがあるかもしれません。 その時、あなたを受け入れてくれる社会は、 どうあるべきなのか、考えてみてください。 「コミュ障な人」の立場になって、考えてみてください。 人は、わからないから不安になるのです。 相手がわからない。 自分が何をしていいのかわからない。 どうすれば、コミュ障な人と、うまく、 コミュニケーションできるのかわからない。 不安を受け止め、乗り越えていくには、 わからないことを わからないまま思考停止して放置するのではなく、 理解しようとすること。 そして、どうすればいいかを 学んで行く姿勢が不可欠なのです。 |
| 2018-10-26 |
自分自身が健康であるために… 昔はすっきりしていたのに、今は疲ればかりがたまる… という行動は珍しくありません。 年齢とともに、セルフケアの方法は変わっていくものです。 体験的に有効だった方法にこだわっていては、 かえって体を傷めることにもなりかねませんね。 難しく考えることはありません。 日々、新しいセルフケアの方法を探して 試していくことを、楽しむようにすればいいのです。 |
| 2018-10-25 |
こんな有名な話があります。 大きな町の入り口で、おばあさんが石の上に座っていました。 そこへひとりの旅人が通りかかり、 おばあさんにこうたずねました。 「これから入っていく町は、いい町ですか? 幸せを与えてくれる町でしょうか?」 おばあさんは答えます。 「あなたが住んでいた町はどうでしたか?」 旅人はこう返します。 「とても嫌な町でした。だから新しい町に移ってきたのです」 おばあさんは、旅人にこう言いました。 「あなたの行く町は、あなたが来た町と同じです」 また、別の旅人が通りかかり、 おばあさんに同じように聞きました。 「これから入っていく町は、いい町ですか? 幸せを与えてくれる町でしょうか?」 おばあさんは、同じように答えます。 「あなたが住んでいた町はどうでしたか?」 旅人はこう返します。 「素晴らしい町でした」 おばあさんはほほ笑んで、旅人にこう言いました。 「あなたの行く町も、あなたた来た町と同じように、 素晴らしいですよ」 |
| 2018-10-24 |
伝える順序 「ほめる(認める、評価する)→「叱る(改善点を伝える)」 の順序が断然おすすめです。 最初にほめたり、認めたりするのは、その後に伝える 厳しいことを受け入れられる状態を本人のなかにつくるため。 いきなり「叱る」から初めてしまうと、そこで心が閉じてしまい、 あとからほめてもそのほめ言葉は心に入っていきません。 さらに言えば、もっとも理想的なのは 「ほめる→叱る→ほめる」というシナリオ。 こうすると、気分のいい状態で面談を終えることができます。 なお、「ほめる」と「叱る」の比率は4対1までに。 この程度であれば、「叱る」による悪い副作用は出ない、 ということが行動科学の見地から明らかになっています。 これ以上「叱る」の比率を増やしてはいけません。 |
| 2018-10-23 |
「信頼される上司」とはどんな人物なのでしょう? 人間的に器の大きい人? カリスマ性のある人? 颯爽とした人? いいえ、こういった人それぞれの好みとは別に、 組織で働くすべての人に共通する 「信頼できる上司の条件」というものが存在します。 それは、 ・自分のことをしっかり見ていて、長所も短所も 把握している上司 ・自分の存在を認め、成長を願ってくれている上司 この2点に集約できると、私は考えています。 ですから、世間で話題になる「理想の上司像」や カリスマリーダーになるといったことは気にせず、 部下の一人ひとりをきちんと把握することだけに 集中すればいいのです。 それなら、今すぐ誰でも取り組めますね。 |
| 2018-10-22 |
生きていくことは、暮らしていくこと。 暮らし、そのほとんどが家事という作業、 主婦(主夫)の場合は。 掃除、片付け、洗濯、炊事… そう、家事とは、メンテナンスの世界。 家族の健康と安全を維持管理するのが家事。 家事そのものが、楽しめるか楽しめないかで、また、 家事が、面倒なものなのか、ウキウキするものなのかで、 「暮らし=人生」は違うものになってしまう。 お料理を、お気に入りの器に盛り付けるのか、 食器には無頓着か、スーパーのお総菜でも、 パックのまんまか、ひと手間かけるか、 そんな小さな積み重ねが、人生の大きな差につながる。 ゆとりがあれば、ひと手間がなんでもないものに。 時間にも場所にもエネルギーにゆとりがあれば。 気持ちにゆとりがあれば。 |
| 2018-10-09 |
評価するときに避けたいのが、去年と今年の比較。 これは、仕事の現場でよく起きます。 去年めちゃくちゃ黒字を出している人がいるとします。 もちろん今年も黒字なのに、去年に比べると足りない。 すると、 「あれ?足りないんじゃない?」 って声が上がったりする。 そのときに、 「もっとできると思ってるから期待して言っているんだ」 なんてフォローして言うのですが、 「いったん、褒めてよ!」 って本人は思っていたりします。 いい成績を見慣れてしまうと、喜ぶレベルが上がったりしがち。 でも、本人にとっては、 ひとつひとつがどれも大事な結果なのです。 現状をしっかり褒めてあげてください。 相手と比較せず、伸びたら褒めます。 褒められることは大事な成功体験です。 「俯瞰(ふかん)」「鳥瞰(ちょうかん)」の視点に立てば、 評価基準はどうとでも変わります。 少しでも上の順位を目指そう!とか、 正しい方向に導いてあげなくちゃいけない! と張り切り過ぎてはいけません。 |
| 2018-10-05 |
約束、つまり目標は 「100%クリアできないと、認めない」 なんて前提で設定しないことが大切。 最初の目標で「一発合格」を強いないこと。 踏まえておかなくてはならないことは、 目標をすべてクリアできる人なんていない、 ということです。 目標は、一方的に押しつけられたものより、 自分が選んだものの方が、 「やる気」が出やすいということを 覚えておいてください。 やる気は本人の中から出てくるものだから、 自分で決めた方が動きやすいですし、 結果を反省するときにも納得して受け止めやすいのです。 それを踏まえて、選択肢を考えて提示してみます。 絶対に選ばないような、思わず笑ってしまうような ものもあります。 大事なのは、その選択肢の中から、 最終的には自分で選ぶということです。 |
| 2018-10-04 |
小さい仕事、たとえば、ちょっとした調べ物、コピー、 届け物、こうした誰でもできる簡単な仕事は、 やろうと思えばすぐにできるし、早くやってみせれば、 大きな仕事を成し遂げたのと同じだけの印象点が得られる。 逆に、簡単な仕事をいつまでも放っておくと 「こんな仕事もできないのか」 と悪印象を残す。 だから、小さい仕事ほど、早く片付けなければならない。 何から片付けたらいいのかわからないくらい仕事が たてこんでいるときは、すぐできる仕事から順に片付ける。 これが、得意先や上司に認められるための 正しいプライオリティである。 |
| 2018-10-03 |
実際には、人生では、 「日頃からきちんと準備しておかなければ、 いざという時に、うまくいかないこと」や、 「そのうちに実行しようと思っているうちに、 絶好のチャンスを逃してしまったり、 チャンスが来ないままで時間だけが経っていること」 が、たくさんあります。 時々、 「いきなりやってみたら、うまくいった」 という体験をしたり、その種の武勇伝を耳にすることがあるため、 うっかり、それを人生の全体に当てはめてしまうのですが、 現実には、そのような幸運に恵まれる望みは、 わずかしかありません。 あなたは、そのわずかな可能性に賭けてしまうのですか? 自分なりに、できる範囲でかまいませんから、 自分の意思と力で、人生を切りひらいてみませんか? |
| 2018-10-02 |
何人ものすばらしいメンターに恵まれたとはいえ、 今日わたしがこうしてあるのは何といっても母のおかげだ。 実際のところ、オクラホマ州の片田舎で育ち、 大学も終えていないわたしのような貧しい少年が、 企業幹部を勤めるまでになったも、よき習慣と自信を 母がせっせと植えつけてくれたおかげだと思うと、 ただただ驚くしかない。 もし会社勤めをしていたら、 母はどんな管理職になっていただろう? いまとなっては知りようもないが、 ひとつだけ言えることがある。 「常に正しいことをせよ」という母の教育方針を、多くの ビジネスリーダーが採り入れようとしているということだ。 わたし自身、立場が上がるにつれて、 基本に立ち返る気持ちがどんどん膨らんでいった。 その基本とは、「母親に言えないことはしない」だ。 |
| 2018-10-01 |
温かく信頼しあえる人間関係を築く。 そんなちっぽけなことが、 実は生きるうえでとても大切だ。 人は、(そのことを) ある日不意に気づかされる。 |