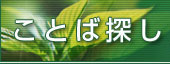■「今日のことば」カレンダー 2008年9月■
2025年 : 1 2 3 4 5 6 72024年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002年 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001年 : 11 12
| 2008-09-30 |
あなたの失敗を見ているのではなく、失敗したあと、 あなたがどう振舞うかを見ている」(略) 素直に自分のミスを認めるかどうか、 シュンとして萎縮してしまうか、 それとも、必死になってミスを取り返そうとするか、 失敗に弱いタイプか、強いタイプか。 失敗後の態度や振る舞いを観察して、その人の 力量や度量を測るひとつの目安にしているのです。 つまり、失敗したかどうかで評価するのではなく、 失敗にどう対処したか、失敗から何を学んだか、 失敗をどう生かしたか、それによって人は評価するのです。 |
| 2008-09-29 |
成功するための両輪ではないでしょうか。 人生においても、自分の血肉となる体験は 非凡な出来事だけから得られるものではありません。 ドラマチックな出来事だけが「体験」ではないのです。 これといって特別なことがない平穏無事な1日からも、 私たちはたくさんの栄養を得ているはずです。 平凡さから得た栄養と、非凡さからもたらされた滋養の間に 差があるわけではなく、平凡な日の積み重ねの果てに、 非凡な1日が訪れてくるのです。 むずかしい球をときどきホームランする打者。 やさしい球を確実にヒットにする打者。 野球にも、こういうタイプの別があるようです。 非凡なひらめき型と平凡な積み重ね型ともいえますが、 私が買うのは後者です。 そこに「平凡のなかの非凡」を見るからです。 |
| 2008-09-28 |
いつもそう思ってください。 むやみに人をうらやむのは大変疲れることなのです。 思うようにできない自分に、腹を立てているので、 よけいに自分を嫉妬させる相手に頭にきます。 発展性のない、自分をつぶしてしまう思いは、無駄なもの。(略) 自分ができないことをやっている人のことよりも、 自分を知って、自分の幸せについて考えてください。 必ず恵まれた部分があるはずです。 |
| 2008-09-27 |
二人が共に自分自身を統合し、 自己実現していくためのレッスンなのです。 それは時に、自我が決めつけている「良いこと」 「正しいこと」の枠組みを超えていることもあります。 今まであなたが安住していた自我の小さな世界が 押し広げられるような痛みを伴う体験です。 自分の価値観が脅かされるような問題が、 次々と浮上してくるのです。 しかしその問題を、苦痛や不運と捉えないでください。 そして、相手に近づき、受け入れ、許すことを選択してください。 自我の価値基準を手放し、パートナーを判断することをやめて、 開いた心で相手に身をゆだねていくとき、 二人の間に大きな癒しが起こります。 |
| 2008-09-26 |
ビシビシ叱り、厳しく鍛え上げてこそ、 人は伸びるし、当人のためにもなる」 と強硬な反対意見を主張する方もいるだろう。(略) しかし、ちょっと考えていただきたい。 みなさんは、他人からの注意や叱責を いつでも素直に受け入れているだろうか? 人間は叱られると萎縮し、批判されるとひねくれ、 難詰されると自分の非は棚上げして、相手に反感や憎しみを 覚えることのほうが多いのではないだろうか。 カーネギーはこう言っている。 「われわれは自分の長所をほめてもらったあとでなら、 いつも少々耳の痛い話でも比較的楽に聞けるものなのだ」 「ほめ言葉で始めるのは、歯医者が治療の前に、 局所麻酔するようなものだ。 患者はあとでガリガリやられるが、 麻酔がその痛みを抑えるのである」 |
| 2008-09-25 |
間違った道を選んだっていい。 後で後悔するかもしれないけど、それも悪くない。 間違った道を選んだからこそ、本当に自分の 進むべき方向がようやく見えてくることだってある。 人と比べてはいけない。 自分は自分の人生を生きているのだと いうことを忘れてはいけない。 人にとっての間違った道が、自分にとっては、 案外、ドラマチックな道かもしれない。 「あれ、道に迷ったかなあ?」なんて 小首をかしげながら毎日を歩いたりするのもまた楽しい。 迷い込んだ道で、偶然、ステキな誰かに出合うこともある。 正しい道を歩いていたら、きっと出合えなかった人だ。 |
| 2008-09-24 |
日常的に使う国に生まれましたが、 この国でなければ学べないことや、 感じられない“しあわせ”がきっとあるはずです。 今、この時代に日本という国に生まれた意味が 何かあるのではないかと思いませんか?(略) 日本に生まれたからこそ、味わえる幸せが たくさんあることにあらためて感謝して、 自分にできることを目に向ける。 そして、自分以外の生命の“しあわせ”も、 自分のことと同じように祈れるようでありたいと想います。 |
| 2008-09-23 |
風を感じましょう 森を感じましょう 海を感じましょう 空を感じましょう 地球を感じましょう 月を感じましょう 太陽を感じましょう 宇宙を感じましょう そして、 風になりましょう 森になりましょう 海になりましょう 空になりましょう 地球になりましょう 月になりましょう 太陽になりましょう 宇宙になりましょう |
| 2008-09-22 |
生まれた直後の親の教育や環境から得たアラヤ識も混在している。 成長して自分で生活するようになってから、 自分でアラヤ識に入れたものもある。 それらが全部いっしょになって原因となり、 現在その結果が花開いているわけで、 先に居座っている因に多分に影響されるのです。 だから、先住のアラヤ識を塗り替えるように、 新たなプラスのタネをせっせとまいていかなければ、 夢はかなわないのです。(略) 考えてみると、この世の中には、 頭がよくても不運な人はいくらでもいます。 それは、アラヤ識の中にいいものが蓄えられていないからです。 いいものを蓄えるためには、最初にタネをまかねばなりません。 アラヤの中にタネをまき、日々それに肥料を与え、 日光を与えて、早く芽を出せカキのタネと念じるのです。 (※アラヤ識(阿頼耶識)=潜在意識 潜在意識のことを仏教では「アラヤ識」と言うそうです) |
| 2008-09-21 |
「文学でもいい、芸術でもいい、いや、 学問でなくたっていい、趣味でも遊びでもかまわないから、 とにかく何かに夢中になること、自分の心や身体が 求めているものにとことん没頭することが大切です」 自分がほんとうに求めている何かを 徹底的に求め抜いていくことが、 その人固有の「ほんとうの人生」、その人の、 「運命の道」と出会う最短の方法の一つだからです。(略) 何でもいい。 一つのことを徹底して求め抜くことで、はじめて、 開けてくる人生の境地というものがあるのです。 |
| 2008-09-20 |
面白いことにこの「stress」の6文字は、それぞれ ストレス軽減のキーワードに当てはめることができます。 「s」 は 「sports(スポーツ)」 「t」 は 「travel(トラベル)」旅行 「r」 は 「recreation(レクリエーション)」娯楽 「e」 は 「eat(イート)」食べる 「s」 は 「sleep(スリープ)」眠る 「s」 は 「smile(スマイル)」笑う (略) 「最近心から笑ったことがない」「面白がれることがない」 というなら、さっそく「ストレス」を「stress」に 切り替えて、この6つの息抜きを生活の中に ぜひ取り入れてみてください。 |
| 2008-09-19 |
他人から評価されようと、自分のことは後回しにして、 人の要求ばかり満たそうとする人もいます。 他人からポジティブな評価をしてもらうことで、 「安心」を得ようとしているのです。 これを続けていると次第につらくなってくるのですが、 やめてしまうと他人のポジティブな評価がなくなって、 もともと持っていたネガティブな自己評価が顔を出し、 さらに苦しむことになります。 こういう人は、自分はダメだと思っている分を、 他人からの評価で補おうとしているのです。 ほかにも威張ることで補おうとしたり、 恋愛にしがみつくことで補おうとしたり、 何か問題を起こして目立つことで補おうとしたり、 アルコールや薬物で補おうとしたりします。 けれども、この「補う」というやり方は、 本物の「安心」の代用品に過ぎないのです。 |
| 2008-09-18 |
「よかったね」と喜んであげよう。 最近、あなたの大切な友達から、 「こんなうれしいことがあったのよ」と連絡があったとき、 あなたはどうしたか、思い出してみてください。 「よかったね」のひと言をいってあげられましたか? 「あまり有頂天にならないようにね」と、 話を腰を折ってしまいませんでしたか? 「よかったね」という1秒の言葉が言えることが大事です。 そこで必要なのは、忠告よりも一緒に喜んであげることです。 特に親しい人であればあるほど、うれしいことがあると、 その人に話したくなります。 人に話すことで、ますますその喜びが大きくなるし、 「よかったね」とその人も喜んでくれたら、 もっとうれしくなります。 |
| 2008-09-17 |
周りから返ってくるものも、 それと同じ高い水準のものになる。 逆にあなたが手を抜き、 仕事ぶりや努力にばらつきが出れば、 それなりの結果を受けることになる。 |
| 2008-09-16 |
落ち込んだときこそ、一生懸命に仕事をすること。 いつにもまして仕事に打ち込むことで、 自分の弱った気持ちを立て直すのです。 うまくいくかいかないかを頭であれこれ考えたり、 想像だけしていても物事は一歩も前へ進みません。 そういうときは基本に戻って、 自分の根っこである仕事や学問に集中することです。 それによって、やはり自分のやっていることには意味がある、 間違ってはいないことを再確認する。 その確信を心棒にして逆風に耐える力とするのです。 |
| 2008-09-15 |
相手も負けずに同じことを主張して、 意見が衝突してしまったことはないだろうか? 一方、向こうの見解にもっと興味を示したら、 自分の意見にも耳を傾けてもらえたのではないだろうか? あるいは、こちらのやり方を押しつけるほど、 逆らってくる人に気づいたことがあるかもしれない。 反面、相手のやり方に任せれば、 もっと素直に接してもらえるものである。 こうして見ると、 他人について学ぼうという意思が受容をもたらすのに対し、 他人をコントロールしようとする意思が、 いかに抵抗を生み出すかが浮き彫りになる。 |
| 2008-09-14 |
選び直す時期があります。 そして、 「本当に大切なものを大切にする」 という新しい生き方へと、 変っていくのです。 |
| 2008-09-13 |
400年の風雪と十数回の落雷にも耐え抜いてきたその巨木が、 カブト虫の大群の襲来によってあえなく倒されたという話を、 彼(カーネギー)は次のように結んでいる。 「私たちはみな、苦闘を続けたこの森の巨人に似ては いないだろうか。私たちは、まれに襲い来る嵐や風や 雪崩や雷からはなんとか生き残ってみても、 結局は悩みという小さなカブト虫… 2本の指でつぶしてしまえそうなカブト虫によって、 心を食い荒らされてしまうのではないだろうか?」 |
| 2008-09-12 |
いつなんどき不当な批判という“にわか雨”に 見舞われるかわからない。 けれども、自分の言動に十分責任が持て、 自分はベストを尽くしたのだと断言できるならば、 それでよしとしようではないか。 つまらぬ言いがかりや難癖の雨が降りかかってきても、 傘をさしてさらさらと受け流しておけばいいのだ。 傘もささずに「この雨をどうしようか」などと 下手に思い悩んでいるから、身体の芯まで ずぶ濡れというはめに陥ってしまうのである。(略) どう考えても自分が間違っていないと確信できるときには、 他人が誹謗の足を振り上げて蹴飛ばしにかかろうと、 世間が中傷の雨を降らせようと、そんなものに いちいち目くじらをたてるのは、 あまりにつまらないことではないだろうか。 |
| 2008-09-11 |
「どこまで行くの?」 「とりあえず、 行けるところまで」 誰でも、すごいことを始めようと 思うと始められません。 ポケットに入っているお金で行けるところまで行く、 という感覚を持てる人が、 夢を実現していくことのできる人です。 行ってみたら、なんとかなるものなのです。 どこまで行けるか、行く前に考えない。 |
| 2008-09-10 |
いざその目標を手中に収めた瞬間、不思議なことに、 「あれ、これだけのことだったの?」と妙に冷めたような、 つまらない気持ちになってしまったという、 そんな経験があなたにもありませんか? ずっと片思いだった恋愛をついに成就させて、 “あの人”を自らの腕に抱いたとたんに、 スッと気持ちがさめてしまった…… これは、とても恐ろしい体験です。 「あれ、私はこの人を愛していたんんじゃないの?」と。 そういう経験があなたにあるかないかは別にして、 これも「あの人が好きだから」という気持ちが、いつの間にか、 「自分のプライドのために、 何としてもこの人を落とさなくてはならない」 という義務に化けてしまっていたことの結果です。(略) 恋愛程度ならまだいいでしょう。 人生の目標を実現させたとたんに、 自殺してしまう人すらいるのですから。 「どうして?せっかく夢を叶えたばかりだったのに…」 と、周囲の人たちは理解できずにいます。 本人としては、「実現したらどんなに嬉しいだろう」と、 ずっと想像してきて、それだけを糧に頑張ってきたのでしょう。 しかし、いざ、目標を達成してみると、とたんに、 「あれ?これだけのことだったの?」 という虚無感に襲われます。 人生をかけて努力してきただけに、 そのギャップの深さに耐えられなくなってしまうのです。 これも、目標に対する愛が、いつの間にか 義務に化けてしまっていたことよるものです。 |
| 2008-09-09 |
「こんな小さなところでは自分の力が発揮できない」 などと考えてしまいます。 「こんな会社じゃ自分を試せない」 「こんな田舎じゃ成功できない」 「こんな奥まったロケーションの店じゃ、客なんか呼べない」 「この程度のチャンスじゃ、たかがしれている」 「こんなわずかな資金じゃ、とてもビジネスはできない」 でも、今のその小さな場所でGOODになれない人が、 どうして大きな舞台でGOODになれるのでしょうか? わずかなチャンスを活かせない人が、どうして 大きなチャンスを形にできるのでしょう? ドデカい仕事で成功できる人は、 小さなつまらない仕事にも全力で尽くした人です。 小さな舞台だからといってバカにせずに、 その小さな場所でGOODになれた人です。 「ちっぽけなこんな場所」だからこそ、 まずはここでGOODになるべきなんです。 |
| 2008-09-08 |
なかなか見つからなくても、今与えられている 業務や仕事をしっかりと行っておくことで、 チャンスの機会は飛躍的に増えることになります。 まず、今の業務を覚える。 覚えた業務について問題意識を持ち、どうせやるなら 自分がその業務を研究するつもりで取りかかり、 試行錯誤を繰り返してひとつの業務に対して信頼を得る。 そして、次の業務へと進んでいく… こんなところから、はじめてみてください。 自分の道は自分しか歩めません。 起業や独立をしなくても、 自分が主人公になれるところを探してください。 そうしたものは案外身近に存在するものです。 |
| 2008-09-05 |
ためらいを覚え、逃げ道を探し、 いつも思いどおりにはいかないものだ。 だが、自主性(そして創造)を持って実行する行為には、 すべて基本的な真理が働く。 断固とした態度をもったとき、 摂理が働きだすのである。 決意することだ。 そうすれば、すべてがよい方へ転がってゆく。 ほかのときでは信じられないような出来事が起るのだ。 それはすべて自分の決意を固めることで 生まれてくる出来事だ。 あらゆる種類の、予測もできなかった出来事、 出会い、物質的援助が舞い込んでくる。 |
| 2008-09-04 |
いろいろな意味があるように思います。 第一に、 やってもやらなくても結果は同じになるということ。 チャレンジには失敗がつきものです。 失敗したら恥ずかしい、努力が無駄になるなど、 マイナス面ばかり考えると腰が引けてしまいます。 そういう人の弱点を克服するためにどうせ、 「同じことならやってみよう」と説く、 【格言】のような意味があります。 第二に、 やってみなければ、決して結果はわからないという意味です。 運がよければうまくいくし、成功する確率も意外と高いかも しれないとプラスに捉えればいいということです。 人は、未来を決して予想できません。 第三に、 やるもやらないも自分の問題で、 他人のことではない、という考え方です。 そのように自分に強く結びつけて考えれば、 成功しても、失敗しても、反省の材料になります。 人の評価で一喜一憂せず、やってみた結果から、 自分の強さや能力を見いだすのです。(略) 心がひかれることがあれば、 ダメでもともとと考えて、チャレンジしてほしいものです。 |
| 2008-09-03 |
こだわっていることをほめられるのは、 「わかってくれて、うれしい!」と思うのです。 がんばっていることをほめると、 努力を惜しまなくなります。 本心でほめたことは伝わります。 また、具体的にほめられると、 納得できるので自信が持てるようになります。 それだけなく、自分のことを見ていてくれたんだな、 という安心感も得られます。 ほめるときには漠然とした言葉でなく、 「こんなところが、いいね」「ここが、気に入った」 どこがよかったか、どう思ったかについて、 具体的にほめましょう。 |
| 2008-09-02 |
人よりもぜいたくをしたい、 人を出し抜きたい…と、 いつも他人のことを気にしていては、 とても 「自分らしく生きる」 ことなどできない。(略) とかく人と自分を比較したがる悪い癖がなくなったとき、 始めて自分とゆっくりと向かい合うことができるし、 自分にとっての一番大切なものを手に入れることも できるのではないだろうか。 |
| 2008-09-01 |
これからは、若い人が 年輩者を部下に持つことが多くなる時代だ。 人には歴史がある。 その歴史を重んじる心がなければ、 その人がもてる力を十分出すはずはない。 若い上司も真に人を生かせる上司になりたければ、 部下の個人史を大切にすべきではないだろうか。 |